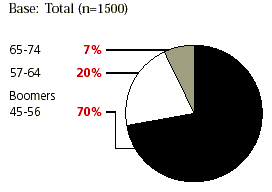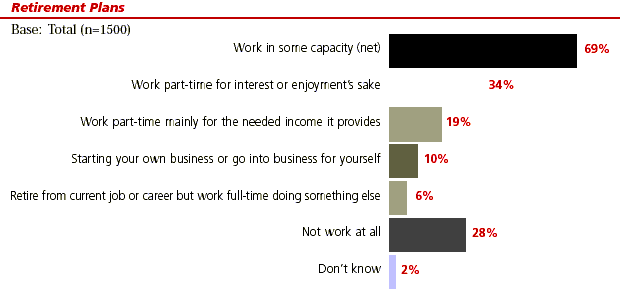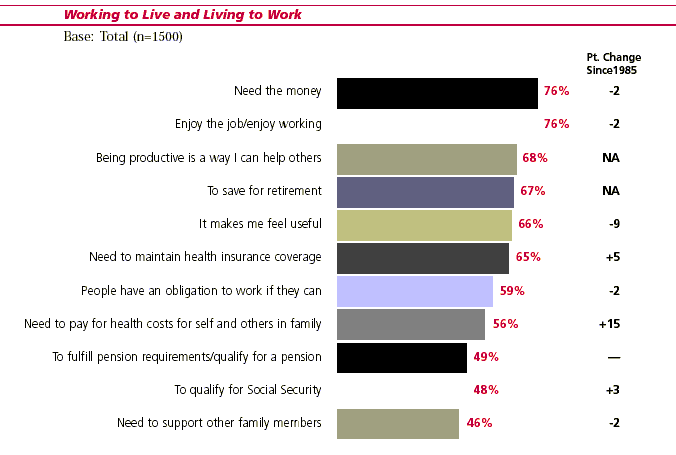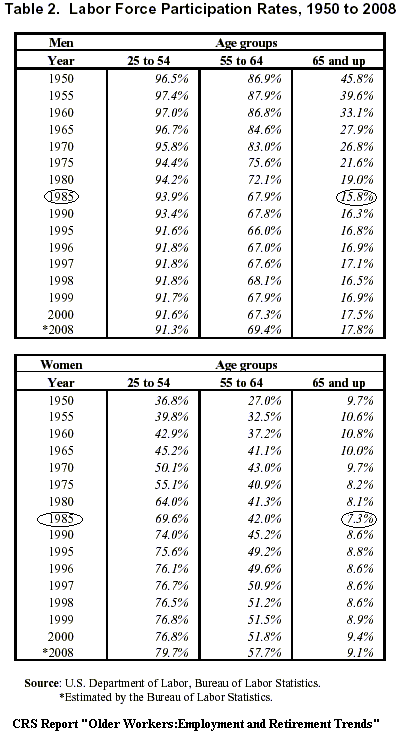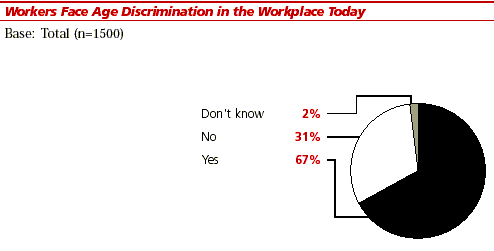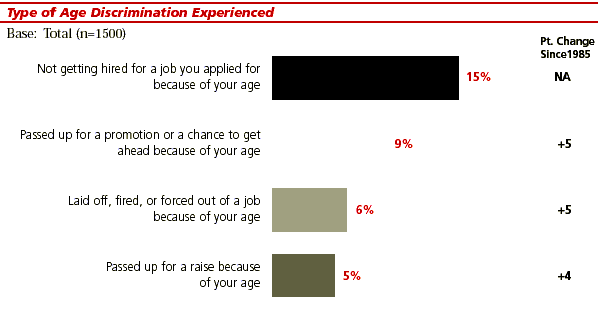Topics 2002年10月11日〜20日
前へ
次へ
18日 労働コストと価値観
18日(2) アメリカの高齢者も働きたい
20日 401(k) なくなった改革ポイント
18日 労働コストと価値観
Source : "Six Dangerous Myths About Pay" by Jeffrey Pfeffer, Harvard Business Review May-June 1998
アメリカにもこんな考え方の学者や経営者、企業がいるんだという親近感を覚える論文を読んだ。タイトルは、「6つの危険な神話。」我々日本人には、当然と思えるところがたくさんあるのだが、アメリカ経済絶好調の最中、つまり買い手市場のど真ん中で、こうした論文をHarvard Business Reviewに掲載する勇気と思い入れには感服する。以下、かなり長くなるが、抄訳を掲載する。
≪イントロ≫
第1問
2つの小製鉄所グループがある。第1の製鉄所グループは、平均時給$18.07を払う。第2の製鉄所グループは、平均時給$21.52を払う。福利厚生などその他の直接的な雇用コストは同じとして、どちらの労働コストの方が高いのか?
第2問
アメリカの航空市場では労働生産性と効率性が競争に勝つポイントとなるが、ある航空会社は、低コスト、低サービスで競争に勝とうとしている。この会社には、成果主義の報酬制度は全くない。この企業は競争に勝てるだろうか?
第3問
競争の激しいソフトウェア分野で、販売コミッション制度のない企業がある。この企業は、個人ボーナス制度もストック・オプション制度もない。有能なプログラマーが不足しているこの業界では、ごく当たり前になっている報酬制度がない。あなたはこの企業に投資するか?
≪6つの神話≫
一般論として、報酬制度については4つの決断が必要だ。
- 従業員にいくら払うのか?
- 全体の報償制度の中で、金銭的な報酬はどれくらいの割合にするのか?
- 賃金率を抑制する努力はどの程度すればよいのか?
- 成果や生産性の相違を評価して従業員にインセンティブを持たせる制度を導入すべきかどうか?また、導入するとすれば、どれくらいの割合にするのか?
報酬制度は、経営者自身が決定しなければならない。報酬制度は、ビジネス活動、従業員の態度、幹部の価値観を左右し、企業文化を醸成する。例えば、カリフォルニアのハード・ディスク・メーカーQuantumは、CEOから時間給労働者まで、全ての従業員を対象に、一律の方式(総資本利益率を基準)によってボーナスを支払うことにより、チームワークを重視する姿勢を打ち出している。
多くの企業が、幹部だけでなく一般従業員についても、ストック・オプションやボーナスのウェイトを高め、基本給の割合を下げているため、報酬制度は多様化している。
また、コンサルタント会社のアドバイスを求めるケースが多くなっているが、そのアドバイスの多くは間違っているため、報酬に関する議論は、不正確であったり、誤っていたりする。その結果、経営者達は、いかに報酬を支払うかという課題について、誤った認識を持ってしまっている。彼らは、報酬に関する6つの危険な神話を信じてしまっている。
あなたは、これらの神話を信じていないか?最初の3つの問いに答えてみてほしい。第2の製鉄所グループの方が労働コストが高いと答えたとしたら、それは、労働(賃金)率と労働コストを混同している。これが、第1の神話「労働(賃金)率と労働コストは同じこと」だ。第2の製鉄所グループの方が第1の製鉄所グループよりも高率で報酬を支払っている。しかし、Fairfield UniversityのProfessor Jeffrey Arthurの調査によると、第2の製鉄所グループの方が労働コストは相当低くなる。それは、第2の製鉄所グループの方が、労働生産性が高くなるからだ。1トンの製鉄を作るのに、第2の製鉄所グループの労働時間の方が34%も少ない。また、途中で排出されるくず鉄は63%も少ない。そのため、第2グループは、19%も高い報酬を支払っても、労働コストは依然として低い。
第1神話に関連して、さらに3つの神話が導出される。第1神話を信じている企業幹部達は、「労働(賃金)率を下げれば労働コストも下がる」と思いがちだ。これが第2神話だ。週給$2,000のエンジニアを週給$500のエンジニアに置き換えることはできる。しかし、そのために、労働コストはとんでもなく高くなるかもしれない。低い給与の従業員は、経験不足で、仕事が遅く、能力もないかもしれないからだ。この例では、労働(賃金)率を下げることで、労働コストを高めてしまっている。
第3神話は、「労働コストは、総コストの大半を占めている」という錯覚だ。時に、この神話は正しい場合がある。例えば、会計事務所やコンサルティング会社の場合がそうだ。しかし、労働コストの割合は、産業、企業毎に大きく異なる。
そして、第4神話は、「低い労働コストこそが競争に勝つ鍵だ」というものだ。品質、サービス、配送、技術開発などによる競争を忘れてしまいがちになる。実際、低い労働コストは、必ずしも競争に勝つことに結び付かず、むしろ競争力の維持を最も難しくすることになろう。
もし、あなたが、低コスト、低サービスで競争する航空会社は個人のインセンティブ制度を導入しなければ成功しないと信じているとしたら、それは第5神話「従業員をやる気にさせ労働生産性を高める最も効果的な方法は個人のインセンティブ制度である」につながる。しかし、Southwest Airlinesは、そのような制度は全く導入してないにもかかわらず、コスト面でも生産性の面でも業界のトップを行く。
従業員にボーナス、ストック・オプション、その他金銭的インセンティブを提供していないコンピュータ・ソフトウェア会社に投資したことがあるか?そのような企業が、過去21年間、年率25%以上で成長している。その会社とは、ノース・カロライナのSAS Institute of Caryである。現在、ソフトウェア業界では最大の民間企業であり、1997年の収入は7億5,000万ドルにのぼる。
報酬制度よりも驚くのは、転職率の低さである。この業界では20%近くに達するのが当たり前だが、この企業では、4%以下となっている。それは、知的な魅力のある仕事、家族生活を大事にする環境、仕事を楽しむ機会、最先端の設備などを提供することにより、実現している。
要するに、SASは、第6神話「人は金のために働く」に陥っていないのだ。むしろ、逆の考え方を採っている。過去3年間、20人いる北米地区担当の営業幹部が一人も辞めていない。同業他社では考えられないことだ。
≪どうして神話が存在するのか?≫
1997年10月10日、the Wall Street Journalは、「天邪鬼Motorolaが、労働"コスト"が高いことで有名なドイツに、携帯電話生産工場を建設する」と、驚きをもって報じた。The Economistも、労働(賃金)率(含む福利厚生)が時間あたり$30を超えていることを指摘して、ドイツの労働"コスト"は高いという記事を書いている。
こうした労働(賃金)率と労働コストを混同した報道が、企業幹部達に2つは同じものと思わせる結果となっている。労働(賃金)率とは、総報酬を総労働時間で割ったものである。対して、労働コストとは、生産性も考慮に入れる。
もう一つの理由は、効果を挙げたい企業幹部にとって、労働(賃金)率は目標としてわかりやすい、ということだ。労働(賃金)率は、計算が容易であり、同業他社との比較も簡単だ。もっと言えば、労働(賃金)率は、企業が最も動かしやすい変動費と見られがちである。生産工程を変更したり、企業文化を変えたり、製品のデザインを変更したりしてコストを抑制するよりも、賃金を下げる方が手っ取り早くて簡単に見える。
「個人インセンティブ制度は創造性と生産性を高める」という神話や、「人は金のために働く」という神話は、経済理論に責めを帰すべきである。特に、ビジネススクールで一般的に教えられている人間行動に関する経済モデルは、困ったものである。このモデルは、人間の行動は合理的である、つまり、その時点で得られる情報をもとに自己の利益を最大化する、との前提に立っている。このモデルに従えば、人々は、金銭的な見返りに基づいて、就職や投じる労力を決定することとなる。仮に報酬が成果に基づくものでなければ、人々は充分な労力を提供しないことになる。
経済モデルでは、仕事は厳しくて嫌なものとして定義づけられている。これは、人を仕事に引きつけるためには、アメとムチを使い分けなければならない、ということを意味する。Stanford Business SchoolのProfessor James N. Baronは、「これらのモデルが想定する労働者とは、ニュートンの第一法則によく似ている。強い力で働きかけない限り、従業員は動こうとしない、というものだ」と評している。
また、経済学用語の「free riding」も影響している。もし、我々が特別報酬を得られる場合にのみ一所懸命働くとしたら、そうした特別報償を常に用意しておく必要があるし、従業員が信用できないということであれば、常に監視をし、従業員を信用できないというシグナルを送り続けなければならない。
(企業の中で)こうした発想がどんどん強くなっているために、それらから逃れるためには、中心的な産業、業界トップの企業に就職することをほとんど諦めなければならない。AES Corporation、Lincoln Electric、the Men's Wearhouse、the SAS Institute、ServiceMaster、Southwest Airlines、Whole Foods Marketなど、相互の信頼と真の分権システムに基づく経営を標榜している企業が、伝統的なビジネス・スクール卒業生を採用しない傾向にあるのは、こうした理由があるからかも知れない。
最後に、報酬制度に関するコンサルティング会社の存在も、これらの神話を助長している。報酬制度の変更は、これらのコンサルティング会社にとっては飯の種であり、彼らが報酬制度以外の改革手段があるとわかっていたとしても、そのような提案をするはずがない。また、報酬制度をいじくることを提案する方が、組織文化、仕事の手順、従業員への信頼を変える提案をするよりも、ずっと簡単である。
≪神話から現実へ:いくつかの例証≫
多くの企業が、労働コストを削減するために、解雇したり、生産現場を労働(賃金)率の低い地域に移したり、賃金を凍結していると、報じられている。例えば、1990年代初め、Fordは、コスト削減計画の一環として、ホワイトカラーの従業員に昇給制度を適用しないこととした。また、1997年、General Mortorsは、外部委託の問題をめぐって、何度もストライキを打たれた。GMは、その労働コストを削減し、より収益性を高めるために、組合によってカバーされていない、より低賃金の業者への外部委託を増やそうとしていたのである。
Fordの決定も、GMの決定も、「動労(賃金)率と労働コストは同じもの」で、「労働コストは総コストの大半を占める」という神話に基づいたものだ。New United Motor Manufacturing(カリフォルニア)というToyotaとGeneral Mortorsの共同出資会社は、1980年代半ばの創業当時、自動車業界で最高の賃金を支払っていた。しかも、従業員に対して雇用の確保を約束していた。同じGMの工場に較べると、生産性が約50%も高かったため、10%も高い賃金を支払いながら業界トップを走っている。
明らかにGeneral Mortorsは、「問題は賃金率ではなく生産性である」という教訓を学んでいない。1996年5月、GMが外部委託問題で労働組合と対立していた際、「Harbour Report」というレポートが、General Mortorsの課題は労働(賃金)率とはほとんど関係ないことを示すデータを発表した。このレポートによれば、一台の車を組み立てるのに、General Mortorsでは約46時間かかるのに対して、Fordでは37.92時間、Toyotaは29.44時間、Nissanzはたった27.36時間しかかかっていない。コスト問題を解決するためには、General Mortorsの幹部は、同じ車を作るのに、なぜFordよりも21%も長い時間が必要なのか、なぜNissanに較べて68%も効率性が低いのか、を問うべきであった。
次に、工作機械産業を見てみよう。この業界の企業幹部の多くは、低コストの外国製品との競争に懸念を抱いている。それは、低コストは海外の低賃金によって実現すると信じているためだ。しかし、労働(賃金)率を固定するのをやめ、その代わりに経営システムや生産工程を全面的に見直した工作機械メーカーは、収益を大きく伸ばす可能性がある。Cincinnati Milacronは、1980年代半ばまでに、高度な技術を必要としない工作機械の分野でアジア企業との競争に敗れて撤退し、生産工程を全面的に変更する、製品在庫をなくす、職種を7つから1つにまとめる、などの改革を行った。増資分を除いて、これらの生産工程の変更だけで、労働時間を50%も削減することができ、企業の生産性は台湾の競争相手よりも高くなった。
アメリカの繊維産業も例外ではない。この業界の企業は、取りつかれたように時間給が低い土地を捜し求めている。しかし、ジーンズ1足を作るのに必要な直接労働のコストは、総コストの約15%に過ぎない。男性用スーツでも、たった$12.50である。
「労働(賃金)率を下げることで優位を保つことができる」という神話について、身近な例で考えてみよう。ある日、買い物リストを持って、大規模ディスカウント・ショップを訪れた。幸いなことに販売員を見つけたので、リストの最初に載っている品物はどこにあるのかを尋ねたところ、彼は「知らない」と答えた。リストの2番目の品物についても同様だった。高い転職率のために、彼自身この店舗に数時間しかいたことがないのだ。このような従業員が、この店舗に必要なのか?彼は商品を売ることができないどころか、見つけ出すこともできない。もちろん、私は、探し回ることに疲れて、何も買うことができなかった。それ以来その店には一度も行っていない。コストばかりで競争しようとする企業は、私のような顧客を失ってしまう。Wal-Martが、低価格戦略とともに顧客に優しい従業員を育て、転職率をずっと低く抑えているのは、決して偶然ではない。
また、Men's Wearhouseは、仕立て紳士服の低価格販売で大成功している。この業界では、激しい競争が行われており、成長の大半は競争相手から顧客を奪うことで達せられる。また価格戦争も激しい。それでも、この企業のパートタイマーは全体の15%以下であり、賃金は業界平均よりも高く、訓練もたくさん行っている。こうした経営方針は、従来の業界のやり方とは異なる。しかし、注目すべきなのは、Men's Wearhouseの従業員コストではなく、従業員に何ができるか、ということなのだ。彼らは製品に関する知識が豊富で、販売技術も高いため、とても効率的に販売が行える。さらに、在庫損と転職率を抑制することにより、在庫減価と採用にかかる費用を節約している。
Fortune1000社について報償制度を調査したレポートによると、従業員の20%以上に個人インセンティブ制度を適用している企業の割合は、1987年から1993年の間に、38%から50%に上昇している。他方、profit sharing制度(より集団的な性格をもつ報償制度)は45%から43%に減少している。また、小売販売業で(歩合制のない)基本給のみの従業員の割合は、1981年から1990年の間に、21%から7%に激減している。
このように任期のある個人インセンティブ制度だが、その問題点は数限りなくあり、多くのレポートがまとめられている。チームワークを阻害する、従業員は短期の雇用を好むようになる、報酬が成果ではなく、人に取り入ることが上手な人に配分されるようになる、などが指摘されており、W. Edwards Demingはじめ専門家はそのような制度の導入に反対している。
成果主義の報酬制度を導入しているSocial Security Administrationの20のオフィスで行った調査によれば、個人インセンティブ制度は、オフィスの効率性に何の影響ももたらしていなかった。他方、出来高制を廃止し、よりグループ指向の報酬制度を導入した、排気システム部品会社を調査したところ、従業員の不満が減少し、品質はほぼ10倍向上した。
また、コンサルティング会社William M. Mercerの調査によると、47%の企業が、「従業員は個人インセンティブ制度を不公平で実際的ではないと感じている」と回答した。また、51%の従業員が、「成果主義による経営は会社のためにならない」と回答した。この調査から、Mercerは、2つの結論を出した。個人インセンティブ制度、成果報酬制度は、大変な時間と資源を必要とし、しかも全員を不幸にする、と。
よりグループ指向の報酬制度にすると、free-rider問題が発生するとの議論があるが、2つの理由から、そのような問題は発生しない。第1に、経済学の書物ばかり読んできた人には驚きかもしれないが、様々な調査から得られた経験則によれば、フリーライディングの程度は極めて限定的である。第2に、個人は、社会的に孤立した状態では、どれだけ努力をしようかという決定は行わない。むしろ、同僚からのプレッシャーや交友関係により、左右される。こうした社会的影響があるために、大組織の中でも、フリーライディング問題はかなり限定されてくる。Profit sharingやgain sharingといったグループ単位の報酬制度を採用している企業の方が、採用していない企業よりも効率性が高い、と指摘した調査もある。
時として、個人インセンティブ制度は、行き過ぎにより、顧客にも悪影響を及ぼすことがある。Searsは、カリフォルニアにある自動車修理店のコミッション制度を廃止せざるを得なかった。それは、コミッションにばかり関心を持つ従業員達が、顧客を騙して不必要な修理を行っていたためだ。また、家電販売のHighland Superstores*も、同様の理由で、コミッション制度を廃止した。
*Website 管理人注:1992年Chapter 11を申請。1993年にChapter 7(清算)へ移行。)
New YorkのRochesterにあるXeroxの企業広報部長Bill Struszは、次のように述べている。「効率性を高める、あるいは組織の問題を解決するために、報酬制度を唯一の手段として利用すれば、2つの結果が出てくる。何も変わらず、大金を費消する。なぜなら、従業員達は、単にお金以上のものを仕事に求めているからだ。たくさんの調査が示している通り、仕事を選ぶ、またはある仕事に留まる決心をする際、お金は決して重要な要素ではないのだ。」
何故、SASでは転職率が低いのかと尋ねられたら、従業員達は、このように答えるだろう。
- 最新鋭かつ最高の技術を利用した設備の中で働ける
- 管理職と専門職の間を自由に往来できる
- プロジェクトが多彩である
- 同僚達が有能で魅力的である
- 企業が従業員の面倒をよくみてくれる
もちろん、SASも相当の給料を払っているが、同業他社に移籍すればストック・オプション等により百万長者になれるかもしれないという業界にあって、従業員を引き止めている要因は、SASの文化であり、金銭的な報償ではない。
人々は、楽しく働ける職場を求めている。それは、AES、Men's Wearhouse、SAS、Southwestに共通しているものである。
≪報酬に関する提言≫
第1に、労働(賃金)率と労働コストの違いをよく理解すべきだ。競争力に関連するのは、労働コストであって労働(賃金)率ではない。ただし、労働コストも総コストの大半を占めるわけではない。
第2に、個人の成果に基づく報酬の効率性に関する神話に打ち勝つためには、報酬制度にグループ指向の要素を多数盛り込んだ場合に起きることを想像してみればよい。企業は、売上、利益、品質、生産性その他の項目について、それぞれの組織がどのような働きをしたか、ほぼ正確に説明できる。しかし、それぞれの要素について、特定の個人がどれだけ貢献したかを説明することは、とても難しく、むしろ不可能といってもよい。ノーベル賞経済学者Herbert Simonが説明しているように、組織に属する人々は、相互依存的な関係にあり、それ故に、組織の成果は、集団的な行動の結果である。もし仮に、個人の貢献度を簡単に計測できて報償を与えることができるなら、それは組織で行う必要がないものであり、従業員それぞれが個人として市場に参入すればよいのだ。
典型的な個人ベースの特別昇給制度の場合、部長は、所轄する部署の全給与の数%増分を予算として配分される。つまり、本質的にはゼロサム・ゲームである。私の昇給が高ければ高いほど、同僚達の昇給は低くなるのだ。同僚達の働きが悪ければ、それだけ私は昇給する。相対評価である。組織のレベルでも同様なことが起きる。決められたボーナスのためのファンドを争うことになれば、仕事で得た経験や知識を、部署を越えて共有しようという気持ちはなくなる。例えば、1995年11月のFortune誌によれば、包装機械メーカーのLantech(ケンタッキー)では、個人インセンティブ制度を導入したところ、そのような内部対立が高まり、会長のPat Lancasterは、「私の勤務時間の95%は、こうした対立の解決のために使われ、顧客のことを考える時間がない」と述べている。
第3に、人は金のために働くという神話に打ち勝つためには、数年前にCompaq(現Hewlett Packard)に買収されたTandem Computerの事例を見るとよい。この企業は、あなたが就職する見込みがつくまで、給与のことは一切口にしない。もしあなたが質問すれば、Tandemは他の企業に負けない給与を払うと説明される。同社は、単純な哲学を持っている。あなたが金のために働くのなら、金のために会社を辞めるだろう。Tandemは、同社の仕事、文化、従業員が好きな人に残ってもらいたいと考えている。また、電力会社であるAES(ヴァージニア)は、比較的早く、企業年金の受給権を与えてしまい、地域の中で最高の給与にならないようにしている。そうすることで、金のためだけに現職を辞められないということがないようにしている。
第4に、報酬制度は、本質的で象徴的な要素を持っている。組織の中で何が、誰が評価されるのかを明確にすることで、組織の文化を決定付けてしまう。従って、報酬制度によるメッセージは何なのか、明確にする必要がある。チームワークと協調を語っておきながら、グループ単位の報酬制度がなければ、問題になる。個人ベースのみの報酬制度とは、組織が本当に重要と考えていることは何なのか、つまり個人の行動と成果が重要だと考えていることを表している。極端な例を挙げると、Whole Foods Marketでは、会社の平均給与の8倍以上の給与は支払われない。その結果、売上高は10億ドル近くあるのに、CEOの給与は、年間20万ドルにしかならない。しかし、1980年代にGeneral Mortorsがやっていたように、従業員を解雇したり、賃金凍結を求めたりしておきながら、幹部に高額の報酬が支払われているということは、適切なメッセージとはならない。Southwest Airlinesは、パイロットに5年間の賃金凍結を求めた際、CEOのHerb Kelleherは、自らの報酬を最低4年間は凍結するよう、報酬役員会に要求した。チームワークの企業文化を創りたいと真剣に求めている企業にとって、運命共同体であるとのメッセージは、強力な武器になる。
また、企業の報酬制度の基本的な考え方を公表することも、強力かつ象徴的なメッセージとなる。職位や職階によって、報酬レベルを公表している企業もあるし、Whole Foods Marketのように、関心を持つ従業員には全職員の報酬データを見せている企業もある。他方、報酬に関する情報をトップ・シークレットにしている企業もある。こういう企業は何をメッセージとして送るのか?給与を秘密にしておくということは、企業に何か隠さなければならないことがある、または従業員を信頼していないということになる。
報酬制度以外にもメッセージを送る手段はある。SAS Instituteでは、自社にとって何が重要で、その理由は何か、ということを、直接従業員に伝えている。そうすれば、報酬制度を変更しなくても、メッセージが伝わり、すばやく変身できる。
報酬制度は、忠誠、チームワーク、成果を左右する経営手段の一つに過ぎない。従って、報酬制度は、他の他の企業内制度と整合的でなければならず、その他制度を補強するものでなければならない。
≪神話を打ち砕くためには慣習を打ち破ろう≫
多くの企業が報酬制度のために莫大な時間とエネルギーを割いているのに、幹部から時間給労働者まで、皆報酬制度に不満を抱いている。これは、人々が報酬に関する神話に挑戦するのを怖れているからだ。他人が何をやっているのかを見て同じ事をするのが、簡単で対立も生まれないからだ。
群れに付き従っているだけでは、莫大な利益は獲得できない。目立つ企業は、慣習にとらわれず、よりよいビジネスモデルを追及していく。報酬に関する神話を打ち砕くことに成功した企業は、報酬制度は信頼に基づく、楽しい、意義のある職場環境には代え難いということを理解している。人件費にいくらかかるかということよりも、従業員が何をすべきなのかを考えることの方が大切である。世間の慣習を打ち破る決断をするのは、企業幹部である。そうすることのできる幹部なら、報酬制度を企業の発展に貢献するような制度にすることができる。過去にこだわる幹部は、いつまでも報酬制度を弄りまわすだろう。そして最後の日になっても、報酬制度を完成することはできず、そのために、莫大な時間と費用を無駄にすることになるだろう。
この論文で、成果に基づく報酬制度は、既にアメリカ企業社会の慣習となってしまっていると指摘している。むしろ成果主義の行き過ぎに対する警鐘として考え置くべきかもしれない。
この論文を読んでいて、面白かったのは、「運命共同体であるとのメッセージ」を送るべきと筆者が述べている点だ。これはまさに、日本企業が今まで培ってきた企業文化だ。日本の場合、それがあまりにも硬直化してしまい、制度疲労を起こしてしまっている。この制度疲労から回復するためには、やはり筆者が述べている「報酬制度は他の社内制度と整合的でなければならない」という点が重要なポイントになろう。経営戦略と人事政策は、こういうところで整合性を求められるのだと思う。
18日(2) アメリカの高齢者も働きたい Source : Staying Ahead of the Curve (AARP)
アメリカ人に『老後の生活はどうしたいか』と質問すれば、『退職後はフロリダに行って、年金生活をエンジョイするのが夢』という答えが返ってくると思い込んでいる日本人は多いのではないだろうか。私も、アメリカに来るまでは、そう思い込んでいた。
今年5月にフロリダに車で行った際、途中のRest Areaで知り合った老夫婦は、まさにそんな夢を実現していた。現役時代は、Baltimore(MD)を生活拠点にして、航空会社(どうもパイロットだったらしい)に勤め、日本にも駐在していたことがあるとのことだった。そして、ご主人が現役を引退した今、フロリダのデイトナ・ビーチの近くに居を構え、たまに孫の顔を見るために、Baltimoreに行っているらしい。
ところが、これから老後を迎えようとする世代、ベビーブーマー達は、少々違う考えを持っているようだ。
上記Sourceは、AARPという高齢者の利益を代表する団体が行った調査の結果である。この調査の対象者は、次の通りになっている。
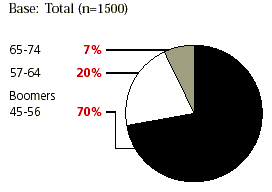
この調査対象の人々に、退職後の生活設計について質問すると、全く働かないという人は、わずか28%しかなく、69%が何らかの形で働きたいと考えている。その目的も、働く楽しみのためという人が34%と約半数を占めており、経済的理由を挙げた人々は19%しかいない。
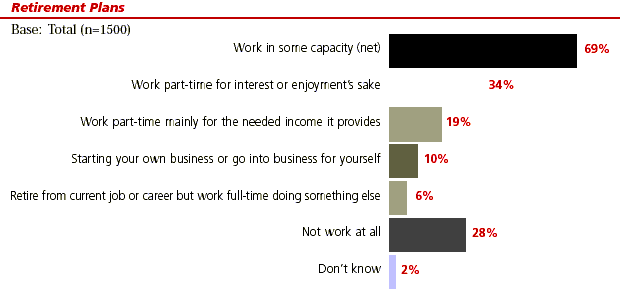
なぜ働き続けたいのかという問いに対して、所得の確保と医療保険の確保を挙げる回答が多いのは当然だが、同時に、働く楽しみのため、社会に貢献するため、自己研鑚のためという理由を挙げる回答も、同様に高い割合を占めている。
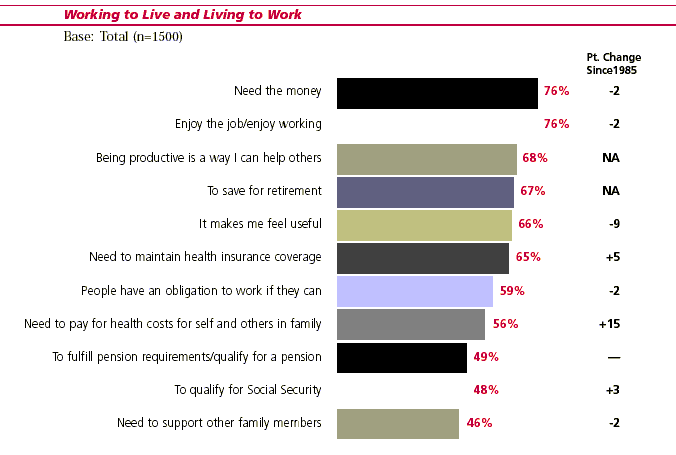
アメリカのベビーブーマー達は、退職後いきなり労働から離れてしまいたくないようだ。こうしたニーズに応じて、企業の側でも、phased retirementとして、退職後もパートタイマーや嘱託、契約社員として、雇用関係を継続する形が増えてきている。この傾向は、実は、1985年を境に、はっきりとしたトレンドが検出されており、今後とも継続すると見られている。
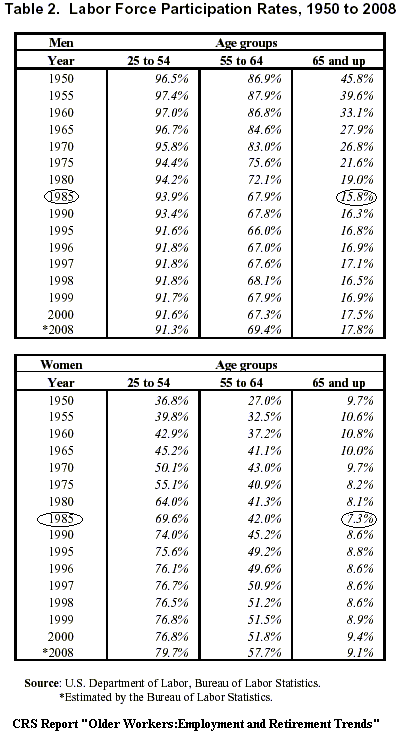
こうした傾向がよりはっきりしてくる中で、課題になるのが年齢差別である。同じAARPの調査によれば、約3分の2が年齢差別を経験したと答えており、その中で最も多いのが、採用の場面である。
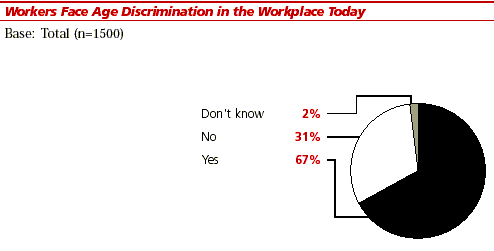
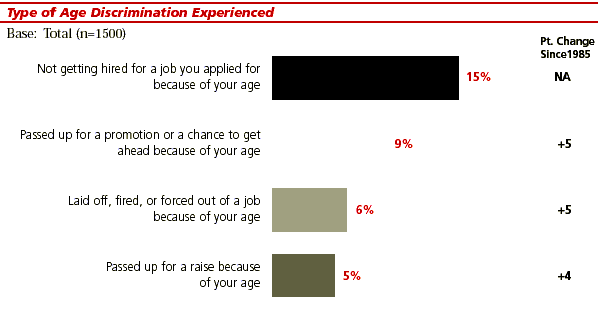
年齢差別禁止法が定められているにも拘らず、こうした差別が続けられている実態は、これから老後に突入するベビーブーマー達にとって、解決すべき最大の課題となろう。
このような課題は、特に働くことが好きといわれている日本の社会でも全く同じことである。企業側は柔軟な雇用形態を用意し、「雇用確保」などという観点ではなく、折角これまで経験と知識を積んできたベテランを有効に活用するとの観点から、積極的に採用していくことが重要だろう。その際、アメリカと同様、年齢ではなく、能力による採用、雇用継続が前提となる。日本でもそうした観点から、年齢差別を禁止(つまりは定年制を違法化)するという政策が必要となろう。
20日 401(k) なくなった改革ポイント Source : Radio Address by the President to the Nation (October 19, 2002) (Whiate House)
先週の土曜日、ブッシュ大統領は、全国向けラジオ演説で、401(k)プランの規制強化策を発表した。これは、昨年12月のEnron倒産事件以来、現実の問題となった、自社株への投資を巡る一連の規制強化策である。
本件について、ブッシュ大統領は、今年2月1日、6つの提案を行った。そのポイントは次の通り。(Topics 2月1日、4日、5日「401(k)プラン改革 大統領提案」参照)
- プラン加入期間が3年を越えれば、企業側から拠出された自社株を他の資産に転換できる。
- Blackout期間中は、従業員(plan participants)と同様、企業幹部についても保有する自社株の売却を禁止する。
Blackoutとは、401(k)プランの運営管理機関(record keeping等)を変更する場合、システムを入れ替えなければならないため、数日間、従業員の資産の転換を停止する措置のことをいう。一般的に行われきた措置だが、Enronの場合、このblackoutの期間が従業員の間に周知されていなかったことにより混乱が生じた。また、本当にこの措置が必要だったのか、株価急落を食い止めるための偽装工作ではなかったのか、などの疑問が残っている。
- Blackoutの開始30日前に、従業員にblackoutを実施する旨通知する。(このような義務規定は今まではなかった。)
- これらの規定を企業が怠った場合、blackout期間中に被った従業員の資産の損失は企業側が補う義務を負う。
- 企業は、従業員に対し、四半期毎に、個人勘定の資産内容、資産残高などを通知する(現行は1年毎)とともに、自社株から他資産への転換の権利の有無、分散投資の重要性を周知させる。
- 従業員が投資アドバイスを受けられるよう、企業側に促す。(この場合、投資アドバイスが従業員の利益に忠実であることが前提となる。)
これらの提案のうち、今年8月の企業不正防止法の成立(Topics 7月25日(1) 「企業不正防止法 」、27日(1)「企業不正防止法案」参照)により、上記2、3が法制化されたため、大統領がこれを発表したという訳だ。
話はそれるが、現在、ワシントンDC周辺は、連続無差別銃撃事件で大揺れである。中間選挙に向けた運動は行われているものの、市民の関心事項は、この事件の動向一点となっている。ワシントン・ポスト紙などには、イラク攻撃の問題、中間選挙の動向などの関連記事は掲載されているものの、あまり大きな関心は持たれていない。特に、テレビのニュースは、連日、この事件の関連ばかりである。
そうした中で、ブッシュ大統領がこんなに細かな提案をいちいち説明するというのは、選挙対策以外の何物でもない。『ブッシュ政権はちゃんと国民、労働者の生活を考えてやっているぞ』、『今はイラクをはじめとしたテロ支援国家をたたく方が大切だぞ』、『安心してイラク攻撃に突き進もう』、ということだろう。ついでに、返す刀で、ブッシュ政権がまともな401(K)プラン規制強化策を提案しているのに、『残りの諸提案を阻んでいるのは、上院民主党だぞ』とやっている訳だ。
さて、今後は、労働省、SECが、上記2つの規制強化策に関する具体的なルールを策定、公表し、2003年1月26日までに施行、という段取りになる。これらの規制強化策について、企業側からの違和感は少ないようだ。実務的に大きな影響を受けるという企業は稀らしい。
ところで、今回の大統領演説(上記Source)を読んでいて、気付いた点が2つある。
第1は、付属のFact Sheetに記載されているのだが、上記3のblackout30日前の事前通告の件である。この通告内容として、Blackoutを実施する理由も含めることになっているのである。これは、上記blackoutの注でも書いた通り、Enron事件の場合、どうしてもblackoutを実施しなければならなかったのか、株価の下支えを狙ってのblackoutではなかったのかという疑問がつきまとっているのである。やはり、そうした疑念は、今でも払拭できていないのだろう。Blackout実施の理由を書かせて通告することにより、こうした疑念への多少の抑止効果が期待できるという訳だ。
第2は、今年2月1日の大統領提案では、改革ポイントは6点あったのに、19日の大統領演説を読むと、5点しかないのである。何時の間にか改革ポイントが一つなくなっている。その落ちたポイントとは、上記リストの4「損失補填」の問題である。同じく、Fact Sheetを読むと、事前通告を行わなかったまたは拒否した場合には、民事上のペナルティ(civil penalty)が課されると書いてある。これがもし、上記4の損失補填を意味するなら、演説でちゃんと最初の通りの6つの改革ポイントを示し、うち3つが実現したと述べるだろう。そうは述べず、しかも、演説内容から落とされているということは、このペナルティはあまり実効性のないものなのかも知れない。21日公表予定の、労働省規則を注目したい。
TOPへ
≪このWindowを閉じる≫
 に戻る
に戻る